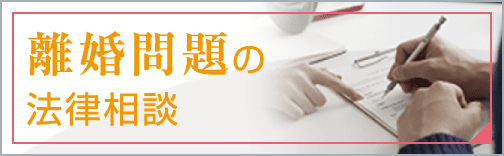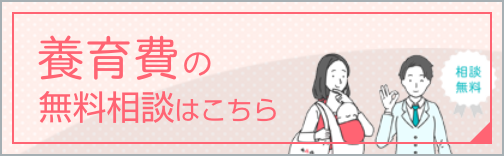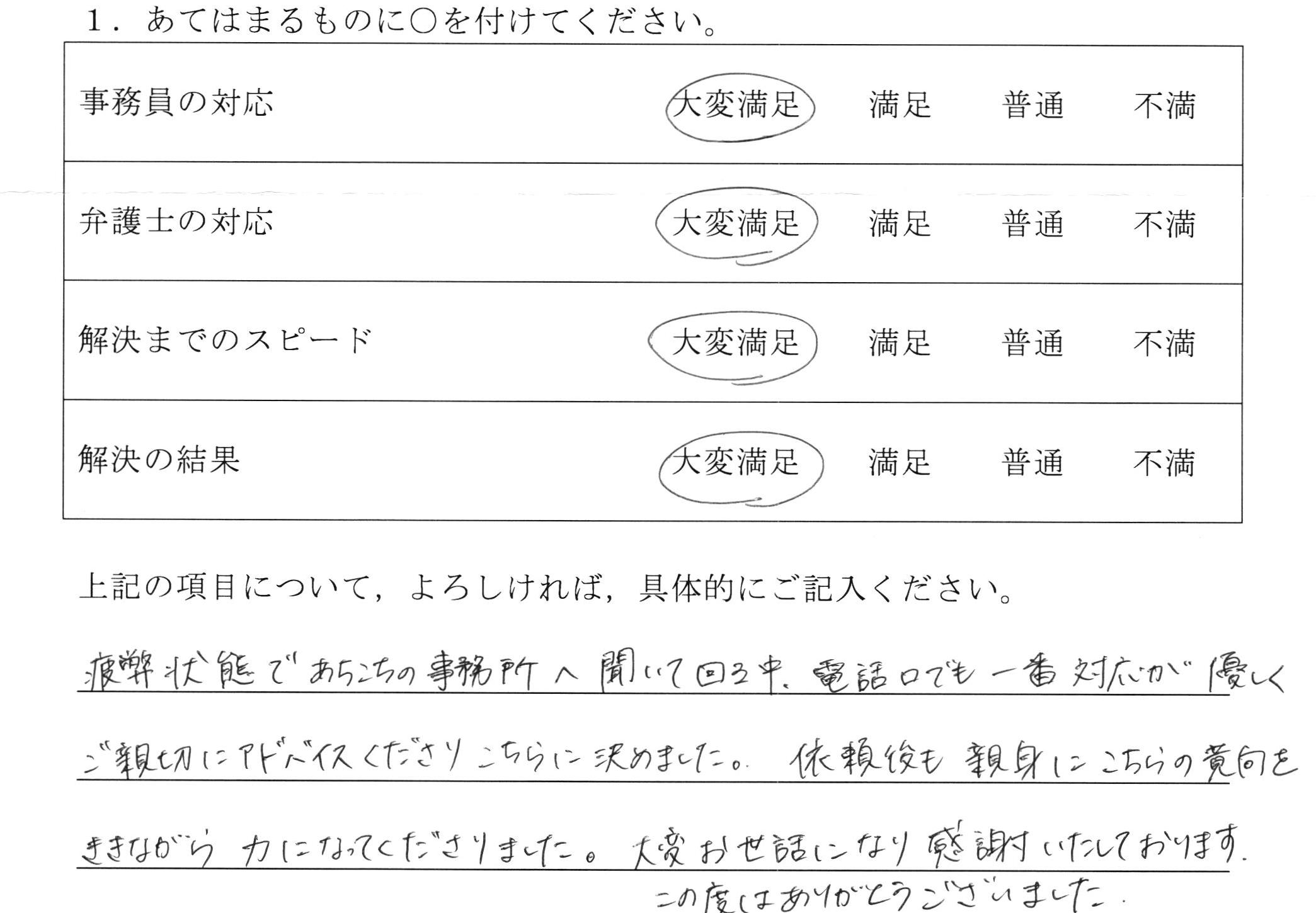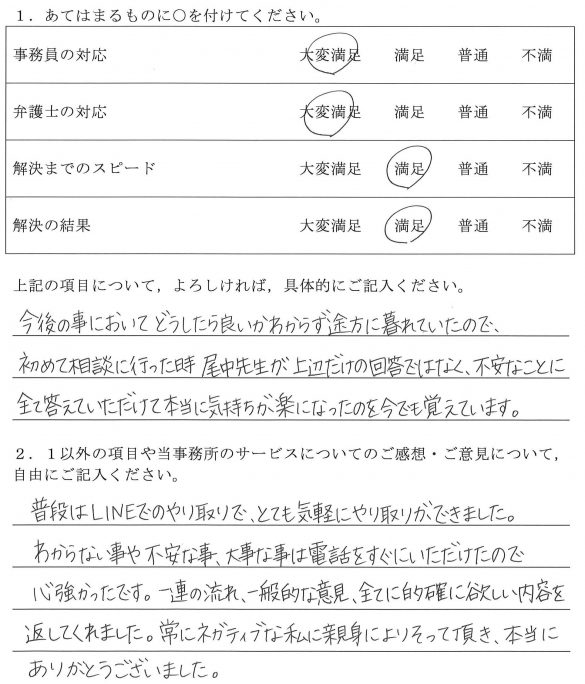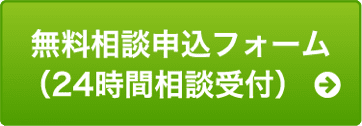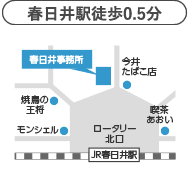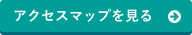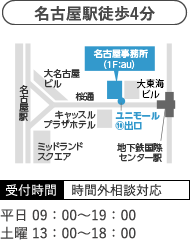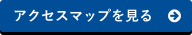協議離婚
| 弁護士がご依頼者様の代理人として離婚協議 | |
|---|---|
| 着手金 | 20万円(税込22万円)~ 御見積 |
| 報酬金 | 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積) |
◆相手と一切かかわらず、離婚を解決したい
など。
着手金について
●親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料も交渉内容に含みます(追加着手金不要)
●離婚協議書や公正証書の作成を含みます
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません
離婚調停(訴訟)
| 弁護士がご依頼者様の代理人として離婚調停(訴訟)を全て対応 | |
|---|---|
| 着手金 | 20万円(税込22万円)~ 御見積 |
| 報酬金 | 20万円(税込22万円)~ + 経済的利益の5%~10%(税込5.5%~11%)(御見積) |
◆協議離婚は自分で対応してきたけれど、これ以上は難しい
など。
●調停3期日分の日当を含みます
●婚姻費用の調停にも対応いたします(追加着手金不要)
●離婚と併せて、調停手続内で、親権、養育費、面会交流、財産分与・年金分割、配偶者への慰謝料を請求できます(追加着手金不要)
報酬金について
●お子様のための養育費については報酬金はいただきません
不貞相手に対する慰謝料請求について
●交渉着手金5万円(税込5万5000円)で対応いたします。